
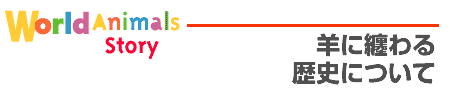
今年の干支に因んで羊のことを考えてみました。
天王寺動物園 園長 中川 哲男
なぜ?日本に羊が畜産動物として広く
定着振興しなかったのでしょうか
 |
|
野生のヒツジの仲間
ビッグホーン |
まず、考えられることは在来の羊が存在しなかったことがあげられます。牛や馬は古くは縄文、弥生の時代に大陸から朝鮮半島、あるいは琉球列島を通じて渡来し、交雑を重ね見島牛、南部牛や野間馬、木曽馬など在来の品種を作り出しています。
しかしながら羊については大陸から同じようなルートをたどって渡来したと考えられるのですが、日本在来種として存在しないのです。歴史的には推古天皇の7年〔599年〕に百済の国から貢物として駱駝、驢馬各1頭、羊2頭、白雉1羽が献じられ、また、嵯峨天皇の弘仁11年〔820年〕に新羅の国から貢物として黒羊2頭、白羊4頭、山羊1頭、鵞鳥2羽が献じられたとあり、醍醐天皇の延喜3年〔903年〕にも唐人が羊、鵞鳥を献ずとあって、その後、何度か輸入の記録が残っています。
その頃、羊を羊毛として利用するにしても、当時の衣服は木綿、麻、絹、芭蕉布などでけものの糸を紡ぐという発想がなかったのかもしれません。また、食肉として利用するにしても仏教による殺生戒や肉食禁忌の教えがあり、受け入れられなかったことが予想されます。
安土桃山、江戸の時代に移って中国、朝鮮、南蛮との貿易で毛織物が一部の特権階級に(例えば、武将の陣羽織や絨毯、ハレの衣装として)輸入されていました。しかし、中には自分たちで羊を飼い、毛織物を生産しようとするものも現れます。文化2年〔1805年〕に長崎奉行の成瀬因幡守が数頭の羊を輸入し中国人の牧夫とともに肥前国浦上村に飼育を開始しますが、失敗をします。しばらくして幕府も江戸小石川薬草園に数10頭の羊を輸入して飼育を開始し、良好な飼育管理によって300頭にまで増える好成績をおさめ、刈り取った羊毛で羅紗を織り将軍に納めたとあります。しかし、その後、文化7年の江戸の大火などもあって衰退消滅します。
羊が大量に輸入されるのは洋種の馬や乳牛と同じように明治維新、文明開化の頃からで、明治2年から次々と輸入されますが、特に明治8年〔1875年〕には下総の印旛郡、下埴郡にまたがる三里塚に広大な御料牧場を開いて、蒙古羊2,500頭、アメリカ産メリノー種500頭、そのほかサウスダウン種、リンカーン種などを輸入し、外国の指導者も雇い入れる大掛かりなものでした。しかし、知識情報の不足と技術の未熟さで失敗します。そして日清、日露の戦争や第1次大戦の勃発で軍需物資の需要から、再び国内での羊の飼育が奨励されます。しかしながら第1次大戦後は安い羊毛がオーストラリア、ニュージーランドから大量に輸入され国内での羊飼育と羊毛生産が低下します。第2次大戦後は食料不足と衣料不足から再び国民に飼育を奨励し100万頭に達しました。しかし、経済が復興安定し羊毛製品の需要が高まると国内で羊毛を生産するより安価で良質の羊毛が大量に輸入され、再び国内の羊毛生産が極端に低下し飼育頭数も減少の一途をたどります。
羊が畜産業として定着振興しなかった原因を推論してみると、日本の国土が狭く、羊の放牧地が十分に得られないこと(牛のように舎飼いが出来ず、羊の舎飼いでは羊毛が汚損して品質の悪いものしか生産できない)、日本の気候風土が羊の飼育に適さなかったこと(高温多湿である)、食肉としても牛と違って臭気がきつく、肉の旨味、芳香が格段に劣り需要が低いことなどと、これらの失敗の繰り返しが日本では羊の畜産業は成り立たないと喧伝されたことなどが考えられます。
このようなことから一時は100万頭を数えた国内の飼育頭数も現在はたったの16,000頭にすぎません。因みに全世界では10億5千万頭、羊毛の主産国であるオーストラリアでは1億2千万頭を保有し、1位は中国の1億3千万頭となっています。
日本への羊毛原料の輸入ランキングではオーストラリアが1位で42%を占め、2位が台湾で16%(主要生産国ではないが原毛を輸入し半製品として日本に輸出している)、3位がニュージーランドで15%となっています。