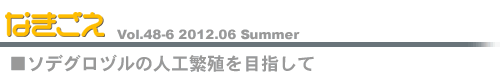

動物園は、来園者にいろいろな動物を見て楽しんでもらう施設であると同時に、自然界で数が少なくなった、希少動物の保全にも力を入れなければなりません。これは文章で書くのは簡単ですが、実際に行うことはとてもむずかしく、実現させるためには綿密な計画を立て、その動物を動物園で殖やし、いつか本来の生息地に戻しても生き延びていけるように、さまざまなトレーニングをしないといけません。自然界は動物園に比べ、はるかに厳しい環境ですから、トレーニングをせずに放しても、すぐに他の動物に捕えられたり、自分で餌(えさ)を採れずに衰弱したりするでしょう。 これまでに、海外の進んだ動物園などでは、自然界でいなくなった動物を動物園で保護し、自然界に戻して成功した例が多くあります。国内でも、豊岡のコウノトリなどは素晴らしい例だと思います。豊岡で野生復帰したコウノトリの一部は天王寺動物園で繁殖したものですが、残念ながら、天王寺動物園は主体となって野生復帰を行った実績はあまりありません。過去にクロサイやホッキョクグマなど多くの種で繁殖実績はありますが、これからはもっと努力が必要ではないかと思います。 2010年よりソデグロヅルの人工繁殖計画に取り組んでいます。このツルはシベリアなどに生息するツルですが、現在はかなり数が減ってしまっています。天王寺動物園では雄、雌ペアで飼育していますが、今までに繁殖した例はありません。相性は良く、毎年4~5月に産卵するのですが、無精卵です。人工繁殖計画とは、このままでは自然繁殖は望めないだろうということで、雄から人工的に精液を採り、それを雌に注入して有精卵を産ませようという計画です。冒頭で書いた、動物園で殖やして自然復帰させる、ということから言うと、全然スケールが小さく、未だにヒナの姿も見ることはできていませんが、今年こそは、と思っています。
人工授精は繁殖期である4月ごろから行いますが、雄から精液を採ることはまずまずできます。問題はそれを雌に注入してうまく授精させることです。ツルはペアをつくって雌雄で繁殖に取り組む生き物です。過去の経験上、ペアの雌が産卵するタイミングに合わせて、雄の精液の状態も良くなってくるのでは?という仮説が立てられています。それとあまり頻繁に飼育場の中に人が入り、ツルを捕まえたりしていると、ストレスがかかり、特に雌の方に悪影響が出て、産卵が遅れたり、通常2個産んで抱きだすのが1個だけしか産まなかったりするということがありました。これは、いろいろな資料を見ると、非繁殖シーズン時でも時々あえて捕まえることで、捕まえられることに、ならすことである程度は解消できるとありますが、当園の個体は飼育係が近くを通っただけで、さく越しに攻撃してくるほどの性格ですから、ならすことは、あきらめて、逆に極力短時間で作業を済まし、速やかに離れるという方法をとることにしました。
雌が産卵する時期が正確に分かれば、その数日前にだけ人工授精をおこなうことで、ストレスを最小限に抑えることができます。これは過去の経験上、巣材を入れておけば、産卵の3~4日前あたりから巣材を一カ所に集めだすことが多かったので、普段からの観察が重要です。それと、今年からの新しい試みとして、雌のふん中ホルモンの値を計り、その変動を見て産卵を予測しようと思っています。血中ホルモンだと雌を捕まえないと採れませんが、ふん中ホルモンだと、雌が排便するのをじっと観察しておく必要がありますが、それをさっさっと回収すれば雌に与える影響はほとんどありません。ただしこのホルモン値が産卵の予測に使えるかどうかはやってみないとわかりません。
今年は4月19日に精液を採取しましたが、性状がよくありませんでした(未成熟精子なのか、生存率は高いが運動性なし)。継続して採精すると造精能が追い付かず授精適期に使えない可能性あるのではと考え、とりあえず雌のふん中ホルモン動態で排卵をモニタリングし、タイミングを見計らって人工授精をする方向で行うことにしました。雌の採便を開始し、まずはホルモン計測が可能かを検証し、しばらくは採精も見送ることにしました。 4月23日に巣材を集め始めましたので、産卵数日前の兆候と考え、4月28日に人工授精実施しました。さらに5月3日に2回目の人工授精を実施しましたがその日に、初卵を産卵しました。6日に3回目の人工授精を予定していましたが2卵目を産卵したので、この日の人工授精は見送りました。その後順調に抱卵していますが、6月10日現在、孵化していないので、今年も成功に至らないかもしれません。
私自身はツル担当ではありませんが、ソデグロヅルの人工授精は、2009年は当時の担当者と調整がつかず、実施できませんでしたが、2010年から始めて今年で3回目の取り組みとなりました。人工授精について、それなりに分かった知見もありますが、もし今年も成功しなければ、人工繁殖の実績のある動物園に、うちのペアを送ることも考えなければいけないかと思っています。天王寺動物園には他にも、たくさんの希少動物が暮らしています。これらの動物たちが絶滅してしまわないように、自分たちの使命をもう一度真剣に考えないといけないと思います。 (油家 謙二) |



