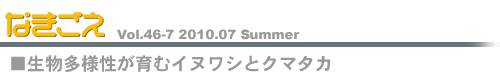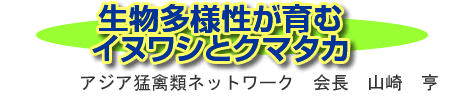|
1.大きくて力強い猛禽、イヌワシとクマタカ
日本は国土の67%が森林に被われている森林国です。その山岳森林帯には、イヌワシ(Aqula
chrysaetos)とクマタカ(Nisaetus nipalensis)という大型の猛禽が生息しています。イヌワシは翼を広げた長さ(翼開長)が2m近くもある、まさに空の王者です。クマタカの翼開長はイヌワシより短く150-160cmですが、翼の幅(翼幅)はイヌワシとほぼ同じ40cmです。つまり、イヌワシの翼はグライダーのように細長く、クマタカの翼は奴凧のように幅広く丸みを帯びています。
2.イヌワシは北方の草原地帯の猛禽、クマタカは東南アジアの森林地帯の猛禽
イヌワシとクマタカは生息場所(ハビタット)や行動も異なります。イヌワシは北半球の高緯度地域、つまり日本より北方の森林が少なく、草や低潅木が生育している地域に広く分布しています。代表的な生息地は、スコットランド、スカンジナビア半島、ヨーロッパアルプス、ロシア〜モンゴルの草原地帯、ヒマラヤ山脈、アラスカ、ロッキー山麓などです。止まり場所の岩山から飛立ち、獲物を探して草原や低潅木の上を飛行し、主にウサギやジリスの仲間などの中小動物を捕食します。つまり、日本のように国土の大半が森林に被われた地域にイヌワシが生息しているということはきわめて珍しいことなのです。
一方、Nisaetus属のクマタカは東南アジアにしか生息しない森林性の猛禽です。最近の遺伝子解析により、かつて日本のクマタカが含まれていたSpizaetus属は中南米のクマタカ2種のみの属となり、東南アジアに分布するクマタカの仲間7種はNisaetus属として独立しました。Nisaetus属のクマタカは、全て亜熱帯〜熱帯雨林に生息する森林性の大型猛禽です。そのうち、日本に生息するクマタカだけが他のクマタカとは異なり、温帯の日本にまで分布域を広げているのです。つまり、日本のクマタカは、熱帯雨林が主な生息域であるNisaetus属のクマタカのうち、北限に生息するクマタカなのです。
3.イヌワシとクマタカの食物
形態や生息場所が異なるということは、ハンティング方法やハンティング場所が異なり、食物も異なることを意味します。
日本におけるイヌワシの主な獲物はノウサギ、ヤマドリ、大型のヘビ類で、これらが食物のほとんどを占めています。一方、クマタカの獲物はノウサギ、タヌキ、テン、ムササビ、リス、ヤマドリ、カケス、ヘビ類、トカゲなど、森林や林縁部に生息する様々な中小動物で、調べれば調べるほど種類は増えています。
イヌワシが限られた種類の動物しか捕食しないのは、イヌワシは飛行しながら獲物を探索することが多く、さらにクマタカと異なって林内に入ることができないため、伐採地などの開けた場所や林縁部、ギャップなどでしかハンティングできないからです。ただし、冬季の落葉広葉樹林のように林内の獲物が見える場合には、1羽が空中で停飛し、もう1羽が獲物を開けた場所に追い出すという共同ハンティングを行うこともあります。
|
落葉した斜面で共同ハンティングを行なうイヌワシのペア |
4.繁殖場所
イヌワシは大きな樹木が生育していない環境に生息しているので、巣はほとんどの場合、上昇気流の発生しやすい急峻な崖の岩棚に造られます。このような条件の良い営巣場所は限られていることが多く、毎年、巣材が積み重ねられるため、巣が縦にどんどんと大きくなる場合もあります。
これに対し、クマタカの生息場所は森林地帯ですから、巣も樹木に造られます。日本のクマタカの巣は直径が1m以上もあるので、巣を架けるには太い横枝が張り出す、とても大きな樹木が必要です。そのような大きな樹木は戦後のパルプ生産や拡大造林政策によって多くが伐採されてしまったため、条件の悪い場所に営巣せざるを得ないことも多く、そのために繁殖が失敗してしまうこともよくあります。
5.人との関わり
イヌワシもクマタカも絶滅危惧種に指定されています。とくにイヌワシは全国で1981〜2005年までの間に43ペアが消失するとともに、繁殖成功率が20%代と低い状態が続いていること(日本イヌワシ研究会)から本当に危険な状態にあります。
はるかな昔から日本人と共生し、天狗伝説の一部でもあったイヌワシがどうして今、絶滅の危機にあるのでしょうか?
私は、その原因は山間部の森林の劇的な変化にあると思っています。わずか50〜60年前の山林はどのような状態だったでしょうか?その頃、燃料といえば炭か薪でした。ご飯を炊くのも風呂を沸かすのも全て森林資源を使っていました。山のいたるところで、炭焼きが行われ、薪が集められていました。また、奥山で生活する人達は、定期的に山焼きを行い、山の斜面で畑作を行ったり、屋根を葺くためのカヤを刈ったりしていました。日本の山岳地帯の多くが里山であり、あちこちに小さな伐採地が点在し、ノウサギなどの中小動物も多かったに違いありません。ところが、石油・ガス・電気が普及することによって、日本人の生活は一変し、燃料を森林資源に求めることはほとんどなくなりました。
そして、拡大造林政策です。1950年代から木材増産のために全国で毎年30万ヘクタールもの山林が伐採され、スギ・ヒノキが植林されました。その結果、2007年には人工林が森林面積の41%を占めるまでになりました。しかも材木価格の低迷によって、多くの人工林が伐採されずに残っているのです。このため、イヌワシやクマタカの獲物となる中小動物が少なくなっただけでなく、イヌワシは獲物を探すこともできなくなってしまったのです。
6.イヌワシもクマタカも生息できる生物多様性に富む森林づくり
日本は生物多様性に富む国です。その多様性の多くは日本人が自然資源を持続的に利用する知恵で管理していた結果として育まれたといっても過言ではありません。山岳地帯に多種多様な生物が生息し、また様々な植生や環境がちりばめられていたために、イヌワシもクマタカも生息することができてきたのです。
せっかくの森林資源。その資源の価値を再評価し、新たな方法でうまく活用することこそが日本の森林の生物多様性を再生することになり、イヌワシやクマタカが悠々と舞う元気な山岳風景を呼び戻すことになるのです。
(やまざきとおる) |