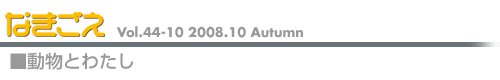
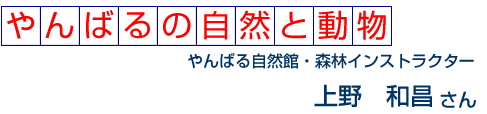
沖縄北部に広がるイタジイの森は古くから人々の生活を支えてきました。琉球王朝の頃、森はきびしく管理されていたといわれています。文化財になっている仲村家の家もイヌマキ等で造られているためにシロアリの被害が少なく現在にもその形を残しています。燃料が薪の時代には、やんばる船と呼ばれた帆船が沖縄北部(やんばる)から薪や材木を運びました。
70年代に入ると、安い材料を求めて紙パルプ企業が南西諸島にやってきました。チェンソーと米軍払い下げの野戦用のトラックと台湾から来た出稼ぎ労働者によって、やんばるの森は姿を変えてきました。 日本に復帰後は、本土に「追い越せ、追い抜け」を合い言葉に国の補助金が沖縄北部にも入り、集落の近くの森が畑に変わりました。比地川の沢登りをしていると私は突然「赤土」で川の半分が埋まった土砂崩れの現場に出あいました。見上げるとブルトーザーが動いていました。自然災害ではなく、畑の造成場所でした。当時は断水が日常茶飯事です。この断水を解消するために、やんばるの森に次ぎ次ぎとダムが造られました。湛水地域は 山頂の近くまで広がります。当然何十haの森が水面に変わりました。 では今日の森はどうなっているのでしょうか、パルプ企業は、もっと南の島に移動しました。強烈なシロアリの生息域のために沖縄では木造住宅はなかなか普及しません。森林組合で働く人も減っています。ダム湖が水をたたえています。人々はきれいな空気や水を求めて、ドライブしたり、心の落ち着きを求めて森の中でトレッキングを楽しんでいます。 これからは元々のやんばるの主人公である動物達が住みやすい森をつくってみてはどうでしょうか、そして人々がその動物たちを見ることができればいいなと思います。インターネットで迫力ある動物たちの映像がありますが、人々が汗をながして歩き、そこで多くの生き物と出会えたらもっと迫力がある思い出ができると思います。 (うえの かずまさ)
|
