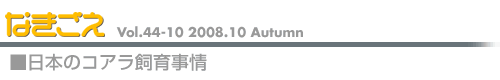|
コアラが日本で飼育されるようになってから24年になります。このためか、オーストラリアの動物といえば、以前はカンガルーでしたが、今ではコアラが一番にあげられるほど有名になりました。そんなコアラの日本での飼育状況をご紹介します。
コアラ飼育園
日本に初めてコアラが来たのは1984年10月25日でした。このときは東京都多摩動物公園、名古屋市東山動物園、鹿児島市平川動物公園の3園で同時に飼育が始まりました。
その後、1986年に埼玉県こども動物自然公園と横浜市立金沢動物園、1987年に淡路ファームパーク、1989年に大阪市天王寺動物園、1991年に神戸市立王子動物園、1996年に沖縄こども未来ゾーンと増えて、現在は9園となっています。
このほかにもコアラの飼育を検討した園はいくつかありますが、コアラの導入が困難なことや餌(えさ)のユーカリを確保する問題があり、簡単には飼育園が増えない状況にあります。
コアラ飼育頭数
コアラは3亜種に分けられていましたが、現在ではDNA検査によりコアラに亜種はなく地域変異とされて、北方系(クィーンズランド州、ニューサウスウェールズ州)と南方系(ヴィクトリア州)に分けられています。日本にも両系統がいますが、今回はコアラ全体数としてまとめました。
1984年に初めて来たコアラは雄ばかり6頭でしたが、翌年には雌5頭が来ました。その後、飼育園が増えるとともにオーストラリアから導入する頭数も増えていきました。また1986年には東山動物園で国内初のコアラが誕生しました。その後、各園で繁殖が順調に行われて、飼育頭数は増えていき、1997年の96頭が最多飼育頭数でした。しかし、それ以後少しずつ減少していて、2007年末には60頭になってしまいました。
そこで、2007年末までの日本での全飼育記録をまとめてみると、海外から導入したのは63頭(オーストラリア62頭、アメリカ1頭)、繁殖頭数は197頭、死亡頭数は194頭、海外への転出頭数は6頭(オーストラリア2頭、アメリカ4頭)です。
コアラ会議
コアラの飼育が始まった頃は、日本で初めての動物を飼育するわけですから、手探り状態でした。そこで飼育園が集まり情報を交換して、協力していくことになり、コアラ会議が始まりました。ここでは飼育係員や獣医師、ユーカリ担当者などの現場関係者が中心となり、飼育技術、病気・治療法、さらにユーカリ栽培について情報の共有化が行われる場となっています。現在は(社)日本動物園水族館協会の種保存委員会コアラ種別拡大会議として開催されています。
第25回会議は今年の7月9・10日に天王寺動物園で開かれました。ちょうどメルボルン動物園から新着したコアラの一般公開式典があり、会議出席者も式典に参列させていただきました。また、会議においてもコアラに同行してきたメルボルン動物園の飼育係員であるチャンディさんに、オーストラリアのコアラ飼育の現状について、お話をしていただきました。
コアラ飼育の課題
1. 繁殖
飼育頭数の減少対策として、以前から行われていたブリーディングローン(BL)が頻繁に行われるようになっています。特に最近は短期BLとして、1頭の雄が複数園に短期間貸し出されて交尾をするという方法が行われて、成果を挙げています。今後もBLは継続して実施していく必要があります。
ただ一方で、繁殖はするのですが、母親の育児のうに入った仔が途中で死んだり、袋から出て落下して死ぬケースが多くなっています。原因として近交係数とか病気などが考えられますが、調査して究明する必要があります。
2.病気
病気としてはクリプトコッカスとコアラレトロウィルスが問題になっています。前者はカビの一種で、呼吸器病や脳炎になり死亡しますが、治療薬もあるので、検査を行って予防することが重要です。後者は白血病や重度の貧血症を起こすウィルスなので、発症すると治療が難しく、すでにオーストラリでも大半のコアラが保有しているといわれ、日本のコアラも保有していることがわかっています。ただ、必ず発症するわけでもないので、むやみに恐れる必要はありませんが、現状を把握しておくことは必要です。このため、両疾病について大学の専門家と共同で検査や対策に取り組んでいます。
3.ユーカリ確保
多くの園が自分の園の近くのほかに他の地域でユーカリ栽培を委託しています。その多くが農家や森林組合などですが、そこでの後継者が不足してきているのが現状です。また、コアラを飼育している自治体等の経済状態が悪くなると、いつもユーカリ栽培委託に影響が出ます。コアラ飼育においてユーカリ確保は必須の課題なのです。
このように日本のコアラの前途は明るいものではありませんが、飼育園が協力しあって、これからもコアラが日本で見られるようにしていくことを願っています。
(はしかわ ひさし)
|