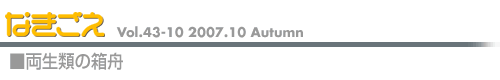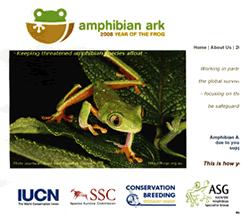|
|
ツボカビ症のカエル
皮膚が侵されるので口を開けて呼吸をしている。
脱皮殻が部分的に残っている。
|
カエルツボカビ症ってなに?
カエルツボカビ症は、ツボカビ菌が両生類の皮膚にとりついておこる病気で、強い感染力と80%にものぼる高い死亡率により、群れの全滅や種の絶滅を引き起こすとても恐ろしい病気です。ツボカビ菌は水の中や湿った泥の中に住んでいて、遊走子という胞子をまきちらして感染を広げます。両生類以外のほかの動物にはうつらず、飼育しているカエルでは治療もできるのですが、いったん野山に広がると根絶することができません。世界中に広がっており、特にオーストラリアとパナマ、コロンビア、エクアドルなどでカエルの絶滅を引き起こしています。
ツボカビ症、日本に上陸
恐ろしい両生類の病気、カエルツボカビ症が、ついに日本で発見されました。昨年12月25日のことです。この病気を調べていた麻布大学の宇根有美博士が東京都と埼玉県の個人が飼っていた外国産のカエルからツボカビ症を確認したのです。その後、日本の数か所からカエルツボカビ症が発見され、外国産のカエルの中にある程度拡がっていることがわかってきました。これを放っておくと日本のカエルがツボカビ症にかかり絶滅する種も出るかもしれません。今、環境省は動物園も含む専門家の力を借りて、全国のツボカビ症の調査を進めています。
カエルを守ろう「両生類の箱舟」
世界のカエルの約半分が、中南米にすんでいます。ところが、中南米では、年間に10種ものカエルが絶滅し続けているといわれています。
1995年にツボカビ症が侵入したパナマでは毎年28kmの速度で南東に向かって広がっています。感染した地域では、生息数が極端に減少し、絶滅状態になるカエルが出ています。そこで、ツボカビ症がやってくる前に、その地域のカエルを国外に運び出し、救出する活動が始まりました。35種のカエルが選ばれ、運び出されたカエルたちは、今、米国・アトランタの動物園で12種が繁殖し、故郷に帰る日を待っています。これが「両生類の箱舟」の活動の一例です。
気候変動がなぜカエルに
2007年のCBSG総会は、「気候変動」がテーマとして取り上げられ、議論されました。このままいくと、21世紀末には1.8〜4.0℃の気温上昇が起こり、アマゾンは乾燥し、北米やインドでは大雨が降るようになるなど気候が変動して生きものが生息地を失ったり、新しい感染症が発生し、大きな影響が出るといいます。鳥は、渡りの季節と子育てに必要な虫の発生の季節がずれて繁殖に失敗するかもしれません。マダガスカルのあるカエルでは、2003年までの10年間で生息する標高が65m高くなったことが紹介されました。気温が高くなると、カエルは山頂に向かって移動しますが、頂上まで追い上げられた後は絶滅しかありません。これが気候変動の影響の一例です。
|