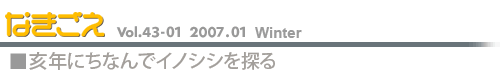
明けましておめでとうございます。今年は亥年(いどし)、にもかかわらずイノシシというと田畑の作物を食い荒らしたり、ゴミを散らかしたり、時には人に咬(か)み付いたりあるいは襲ったりと、最近は害獣、悪者のイメージが強くなる一方です。そのためか一般の人にはどうも親しみがもてない動物の一つなのかもしれません。しかし12年に一度巡ってくる主役の年ですから、イノシシが親しみにくい要因は何か、イノシシとはどんな動物なのか、探ってみることにしましょう。
一方、イノシシはといえば森にすみ、首や四肢は短くずんぐりした体つきで目も小さく、どちらかといえば鋭い目つきです。鼻もシカやウシの触ってみたいような鼻鏡に比べ、イノシシは鼻の先端が切り落とされたような円盤状の鼻鏡に鼻の穴が大きく開いています。俗にいうブタ鼻というものです。愛嬌(あいきょう)があってかわいいといえばかわいいのですが、どうひいきめに見てもイノシシが一番かわいいという人はいるとは思えません。ところで体つきからお分かりのように、偶蹄類のなかでイノシシと近縁な動物はカバなのです。しかしカバは小さな耳とぎょろっとした目、大きな鼻と口、なんとなくユーモラスですし、短い四肢にも愛着を感じさせる大型動物です。
話はそれますが、ブタはイノシシを先祖とした動物で、8千年以上前からヒトによる飼育が始まり、家畜化されてきました。どちらも上質な肉を提供してくれますし、両種は体色が異なること以外にも、ブタは尻尾(しっぽ)がくるくるとカールし、耳の垂れたものが多いのですが、イノシシでは尻尾は垂れ下がっていますが耳は直立しています。この両種の間にはイノブタと呼ばれる雑種もできます。イノシシとブタの先祖は同じイノシシですから、分類学的には同じ種類になります。ですから雑種という言葉は正確には間違っているのですが、一般には雑種イノブタで呼ばれています。イノシシの肉は牡丹鍋として高い需要があるのですが、狩猟に頼らねば確保できないことから、養豚技術を応用してイノブタの飼育が始まりました。ちなみに日本では亥年の動物はイノシシですが、十二支の動物を考え出した中国ではブタを指しています。
ところで日本にすむイノシシは、実は日本を含めたアジア、ヨーロッパ、北アフリカに広く分布しており、生息する地域によって大きさや毛色、生態などが異なることから亜種として分けることがあります。ヨーロッパイノシシ、スマトライノシシ、タイワンイノシシなど20ほどの亜種に分けられます。大陸にすむイノシシは150kgから200kgもある大型ですが、日本のものは小型です。この狭い日本には2つの亜種、ニホンイノシシとリュウキュウイノシシが生息しています。ニホンイノシシは本州、四国、九州、淡路島に分布し、北海道にはいませんし、本州も日本海側や東北地方の豪雪地帯には生息していません。足が短いため、雪深いところでは歩き回ることができなくなるからです。しかし地球温暖化の影響でしょうか、分布に変化が認められだしました。福井県の山間部や宮城県仙台市の山地での生息が最近確認されています。
もう1つのリュウキュウイノシシは奄美(あまみ)大島と沖縄の南西諸島に分布するさらに小型のイノシシで、ニホンイノシシの体重約100kgの半分ほどしかありません。天王寺動物園ではこのリュウキュウイノシシを飼育し、4年連続して赤ちゃんが誕生したことがあります。イノシシの赤ちゃんというのは体に沿って10本ほどの白い縞模様(しまもよう)があります。生後4カ月ほどでこの模様は消えてしまいますが、その姿がシマウリに似ていることからウリ坊と呼ばれています。森の中で生活するイノシシにとって木洩れ日の下ではこの縞模様が格好の保護色になっているのでしょう。母イノシシが横たわって子ども達に授乳している姿は本当にほほえましいもので、悪役のイメージなどまったく感じさせないすばらしい光景です。 (天王寺動物園長:宮下 実) |



