
 |
開園90年を迎えた日本で3番目に古い歴史を持つ天王寺動物園ですが、その発祥の歴史は先行2園と同じように内国勧業博覧会跡地に建てられ、周辺には博物館、美術館があり、緑豊かな公園の一部に位置するなど近似した軌跡を描いています。また、博物館施設の一部を継承したところは上野動物園と同じですが、博物館自体の運営形態が違って、前身の府立大阪博物場は江戸時代の見世物の名残を色濃く残しており「大阪最大の楽園」と揶揄されるほどでした。西日本、特に関西圏の動物園が見世物興行の性格をいまだに残していたのは、自由闊達で先取の精神が旺盛な商人で成り立つ都市であることや、江戸・東京のように政治を司る役人の都市ではないことから、学問研究というより入園者を喜ばせ、満足させる運営形態となったのではないでしょうか。天王寺動物園の戦前のスーパースター、チンパンジーの「リタ嬢」や戦後の「ライガー」づくりなどは如実にそれを物語っていました。戦前、京都帝大教授で京都市動物園長の川村多実二や大阪市立動物園の筒井嘉隆らは、動物を見世物にし、学術的意味がなく知識階級から無関心を招来するような堕落であると慨嘆しました。
戦後も落ち着き、高度成長の時代に入った1980年頃より、天王寺動物園では展示の改革を推し進めました。本格的なガラス式猛獣舎・ヤマネコ舎、ウォークスルーの巨大なバードケージ、そして全園的な整備計画であるZOO21計画に基づく「水中透視のカバ舎」、「アフリカサバンナ区草食動物ゾーン」などは関西人の特質としての先取の精神を発揮し、時代を先取りしています。ここに来て天王寺動物園がようやく見世物動物園から脱皮し、日本の動物園界をリードする動物園として変身したのです。また、世界的な動物園としての評価を受けるためWAZA(世界動物園水族館協会)への加入を推進し、西日本で唯一の加入園となりました。今後も天王寺動物園は飛躍的に発展していくと思いますが、動物園のあるべき姿として、1.入園者に大きな感動と喜びを与える。2.動物が健康で生き生き輝いており、行動が豊かである。3.豊富な情報を提供し、サービス性に富んでいる。4.安全である。5.教育的配慮がある。6.園の持つビジョン、コンセプト、ポリシーを職員が認識し、共有する。などを堅持して行かなければならないと思います。
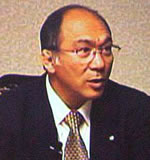 |
旭山動物園は日本最北の動物園として、1967年にオープンしました。当時はどこの動物園でも、絵本の中の野生動物が生きて目の前にいることだけで、多くの人々が訪れていました。しかしながら1980年代になると、各地で博覧会が開催され、テーマパークも相次いで営業を始めました。その影響を受けて各地の動物園は入園者数が減少し、旭山動物園も存続が危ぶまれる状況となってしまったのです。
その時期、我々は動物園の歴史を辿り、その役割の変化を確認しながら、動物園が現在、そして未来に向けて必要とされるような活動を模索していました。そして,動物園とは、野生動物の種の保存を大きなテーマとし、野生動物の魅力を伝えることで多くの人々が野生動物との共生を願うような社会となるように働きかけることが最大の使命であると考えたのです。
動物とは“動くもの”であり、動きの中にこそ人は動物の魅力を感じるものです。ただし、動物園の展示である以上,その行動は、野生動物が進化の過程において種として獲得した行動でなければなりません。そして、その行動が、野生動物の特徴的な形態の意味を表しているものであることが必要です。
我々は,これまでも飼育動物の福祉という観点から、環境エンリッチメントの手法を用いて,動物たちに行動の目的やきっかけを与える手法を研究してきました。それを展示に生かすことで,動物たちが本来持っている能力を遺憾なく発揮している瞬間を,入園者に直接観察させることができると考えました。
旭山動物園では,動物のすごさに感動していただき、野生動物を尊敬していただくことで、多くの人に,野生動物の保護さらには野生動物を育む自然環境の重要性に関心を持って頂きたいと願っています。それが旭山動物園の『行動展示』なのです。
 |
「今日、わたしたちの多くは都会に住み、野生動物や植物との本来の関係を見失っています」。世界動物園水族館協会(WAZA)が2005年5月に作成した「世界動物園水族館保全戦略2005」の序章で紹介しているディビット・アッテンボローの言葉です。生き物であるはずの人が、生き物との関係がないところで生きている―これは大変なことです。日常から生き物が絶え、身近な生き物の宝庫である田園や河川、里山から子どもたちの遊ぶ声が消えて久しくなっています。地方都市の富山においても例外ではありません。富山にいて同じ空気を吸い、同じ水を飲む生き物たちと、その生き物が暮らす場を知ってもらう動物園作りができないかと考えました。
日本産の動物収集、展示事業に始まった富山市ファミリーパークの歴史は、普及啓発事業へ、さらに園内の自然調査、保全と活用事業へと拡大してきました。1999年、市民が作り、進める動物園を目指したZOO夢21(ずーむにじゅういち)市民計画を開始しました。さらに里山再生のための「市民いきものメイト」が結成されました。会員たちは里山再生活動や、来園者に対する普及啓発活動を行っています。今年4月にはファミリーパークがアースデー会場となり、いきものメイトと市民ネットワークによる来園者との1万人の交流も行ないました。
一方、動物園側も図鑑的な展示をやめ、多様な来園動機を発掘しようと展示を一新しました。総合テーマは、「日本へのはるかなる動物の旅―故郷富山再発見」で、5つの視点で構成されています。第一は、いき残りへの道―生き物の形と進化。第二は、動物飼育のいま・むかし―人に役立ってきた家畜、動物園の動物たちの歴史。第三は、昔を生きた動物 今を生きる動物―絶滅のおそれのある動物、これからの共存を考える。第四は、日本人といきものたち―生活や文化、民俗学と動物。第五は、発見!呉羽の森―身近な自然の発見。この5つの視点から富山の動物を伝えようというものです。それぞれのシンボルマークをたどれば園内を5つのコースで巡ることができます。
ファミリーパークが進む道は次のように集約できると思います。動物や動物の棲む環境を知り、体験し、考え、自分たちで動物たちにできることを見つけ動こう。里山を園内で再生し、その展示や活動体験を通じ、来園者に理解と参加の輪を広げよう。自らを担い手とする自然と共存する社会づくりに、動物園は寄与していこう。動物園は、自然と人をつなぐ場、地域に生きる施設。そうすれば、森(里山)も動物も元気に、そして人も元気に、きっとなるだろう。
