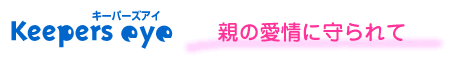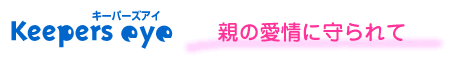クロエリセイタカシギは、北アメリカから南アメリカ北部の、浅い水辺のあるひらけた土地に生息しています。名前の通り脚が長いので、水の中でも、体をぬらさずに餌をとることができます。動物園では、カワエビやペレット、コオロギなどを与えています。オスの背中の羽は、少しつやのある真っ黒な色で、メスの背中の羽は、茶色がかったつやのない黒色です。また、オスの方が少し大きな体格をしています。
クロエリセイタカシギは、北アメリカから南アメリカ北部の、浅い水辺のあるひらけた土地に生息しています。名前の通り脚が長いので、水の中でも、体をぬらさずに餌をとることができます。動物園では、カワエビやペレット、コオロギなどを与えています。オスの背中の羽は、少しつやのある真っ黒な色で、メスの背中の羽は、茶色がかったつやのない黒色です。また、オスの方が少し大きな体格をしています。
春から初夏にかけて、クロエリセイタカシギは繁殖期(卵を産み、ヒナを育てる時期)をむかえます。この時期になると、オスとメスが共同で、小枝や草の茎、小石などを集めて地面に巣をつくります。そこに、黄土色に茶色の斑点のはいった卵を4個ほど産み、交代で25-26日間あたためます。このときに、飼育係が何度も部屋に出入りすると、安心できないために、卵をあたためるのを途中でやめてしまうことがあります。このため、できるだけ出入りを最小限にして、掃除もひかえなければなりません。
ヒナが誕生すると、親鳥は自分の子どもを守るためにとても神経質になります。飼育係が部屋に入ろうとすると、自分より何倍も体の大きい私たちを追い払おうと向かってきます。油断していると、長いくちばしでつつかれそうになります。親の愛情ってすごいですね。このとき親鳥たちは、「ケッケッケッ…」と甲高い警戒の声をあげます。生まれたばかりのヒナたちは、この声を聞くとその場にうずくまって身動きひとつしません。ヒナたちの羽毛は卵と同じような色で保護色になっており、動かなければ地面と見分けがつきません。このため、敵に見つかりにくいのです。ところが、ひとつ落ち度があります。ヒナたちは、警戒の声を聞くと、いつでもどこでも地面に身をふせるのです。それが飼育係の足元であろうとも。これでは“まるばれ”です。おせっかいながら、もう少し隠れることのできる場所に逃げこんだ方がよさそうなのになぁ、と思ってしまいます。
(飼育課:中島 野恵)