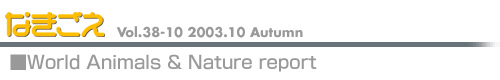

大阪のコウモリを調べる会 浦野 信孝
| はじめに 大阪でコウモリ?大阪のコウモリを研究しているという話をすると必ず、「夏の夕方、街灯の近くを飛んでいるね」という答えが返ってきます。都会で飛んでいるのはアブラコウモリという、家屋や橋の下などの人工物に棲んでいるコウモリです。街灯に集まってくる蛾やユスリカなどを食べているのです。私たちは洞穴性コウモリという、主に廃坑や鍾乳洞などの洞穴に棲むコウモリを調べています。 |
 |
|
写真1.キクガシラコウモリ
熟睡すると翼で体を包んで寝ます。 |
コウモリの種類
日本には34種類のコウモリが棲んでいます。これは齧歯類の27種類より多い数で、日本の哺乳類の約3分の1を占めています。オオコウモリは南西諸島や小笠原に分布し、昼間に視力を使って活動しています。コウモリの大部分を占める小型のコウモリは日本全国に生息していて、超音波を使って夜に活動し、昆虫などを食べています。小型のコウモリはその生活様式から、木のほこらを利用する樹洞性コウモリ、人工洞や鍾乳洞などの洞穴を利用する洞穴性コウモリ、家屋を利用する家屋性コウモリなどに分類する場合もあります。時期によりそれらの穴を使い分けているコウモリもいます。
穴を捜す
大阪には鍾乳洞などの自然洞穴はありません。コウモリの生息は、廃坑や防空壕などの人工的な洞穴に限られます。大阪府北西部と兵庫県南東部をあわせた地域は北摂山地と呼ばれ、江戸、明治から昭和初期に採掘された鉱山跡が多数残っています。
穴探しは資料探しから始まります。郷土史や鉱山の資料、地質図に残された鉱山マークをもとに現地まで足を運び、穴を捜します。たいていは道もない山中です。ズリ(放置された、鉱山から掘り出された鉱石を含まない岩石や土砂)が見つかればあと一息です。その上部を探すと坑口が見つかります。ほとんどは自然に埋まったり、人為的に閉鎖されたりしていますが時々、そのまま放置された坑道が見つかります。
 |
|
写真2.坑 道
会員の藤田氏が坑内を調査中。 コウモリの入った袋が見える。 |
北摂の鉱山は明治時代の手掘りのものが多く、細い鉱脈に沿って這って歩くような坑道が延々と続いています。数mの試掘坑や途中で落盤により埋まっているものも多いですが、中には200mを越える坑道が残っている場合があります。約30カ所の廃坑と50を越える坑道を発見し、半数以上でコウモリの生息を確認することができました。それ以外には防空壕やダム導水路、ダム試掘坑、旧道のトンネルなども調査しました。
大阪のコウモリ
調査の結果、キクガシラコウモリ、コキクガシラコウモリ、モモジロコウモリ、ユビナガコウモリ、テングコウモリの5種類が見つかりました。
キクガシラコウモリは奇妙な鼻をしています。(写真1) これは超音波を出すときに、パラボラアンテナのように焦点をしぼって発射するのに役立っていると考えられています。熟睡すると翼で体を包んで寝ます。これはキクガシラコウモリに特有です。コキクガシラコウモリはキクガシラコウモリをそのまま小さくしたようなコウモリです。冬でも暖かい、洞穴の奥の方に棲んでおり、冬でも活発に活動しています。
モモジロコウモリはアブラコウモリに似た小型のコウモリです。季節によりオスとメスは別々のコロニーを作ることが多く、北摂ではメスが多く見つかっています。ユビナガコウモリ(写真3)は、大きなコロニーを作ることが多く、北摂でも200頭を越えるコロニーが見つかっています。長距離を移動するコウモリとしても有名で、山口県では100km以上の移動が確認されています。テングコウモリは環境省では希少種に分類される個体数の少ないコウモリです。樹洞性コウモリに分類されますが、冬期間にのみ洞穴を利用しています。大きなコロニーは作りませんが、数カ所の洞穴で確認されています。
生息地の調査とあわせて、現在はバンディングによる移動調査を行っています。翼をはさむようにアルミリングを付けることにより個体識別を行う方法です。今までに能勢町から箕面市までの数kmの移動が確認されています。

写真3.ユビナガコウモリ
堺市内でヒナコウモリ発見
 2003年7月に堺市東三国ヶ丘町の民家でヒナコウモリ(写真4)が発見されました。ヒナコウモリはテングコウモリと同様に希少種に分類される、数の少ないコウモリです。近畿地方では比叡山や福井県の小さな島などで見つかっているだけで、もちろん大阪では初めての記録です。
2003年7月に堺市東三国ヶ丘町の民家でヒナコウモリ(写真4)が発見されました。ヒナコウモリはテングコウモリと同様に希少種に分類される、数の少ないコウモリです。近畿地方では比叡山や福井県の小さな島などで見つかっているだけで、もちろん大阪では初めての記録です。
ヒナコウモリは繁殖期にメスだけが集まり、民家の屋根裏に大きなコロニーを作ることが多く、今回の例でも7月上旬に最大270頭の出巣が確認されました。通常、母親は2頭の子どもを産むので約100頭のコウモリがお産のために集まってきたと考えられます。日暮れ直後から約30分の間に、200頭を越えるコウモリが鳴きながら(ヒナコウモリの声は人間の耳に聞こえるのです)出ていくのは感動的な場面でした。
子供が大きくなるにつれて母親、子供の順にコロニーを離れ、8月にはコウモリはいなくなりました。このコウモリ達がどこから来たのか、どこへ分散したのか、今年も帰ってくるのかどうか、大変興味があります。
ヒナコウモリはアブラコウモリよりかなり大きく、銀色の刺し毛が背中に見られるコウモリですのでよく見ればわかると思います。また、一部のコウモリにはバンディングしましたので、もし、死体などを見かけられましたらご連絡くだされば幸いです。
コウモリのこれから
坑道が残っているという資料を基に調査しても、実際に現地へ行ってみるとすでにコンクリートで蓋(ふた)をされていたり、埋め戻されたりしているケースがよくあります。また、住宅開発で消失した廃坑も多くあります。
キクガシラコウモリは1頭あたり1日に、体重の約30%、すなわち平均体重を20gとすると6gの昆虫を食べる計算になります。100頭のコウモリが6ヵ月間活動すれば6g×100頭×6ヵ月×30日=108kgもの森林害虫である昆虫を食べている訳です。コウモリを保護するということはすなわち、森林を守るということにつながるのです。危険だから蓋をするというのではなく、コウモリの生活にも気配りして格子状の柵をするなどの配慮が欲しいものです。
活動時間が夜間なので目にする事は少ないかもしれませんが、コウモリの生息環境を守り、森林の害虫駆除に大きな役割を果たしていることを理解し、大阪近郊のコウモリを見守ってあげてください。